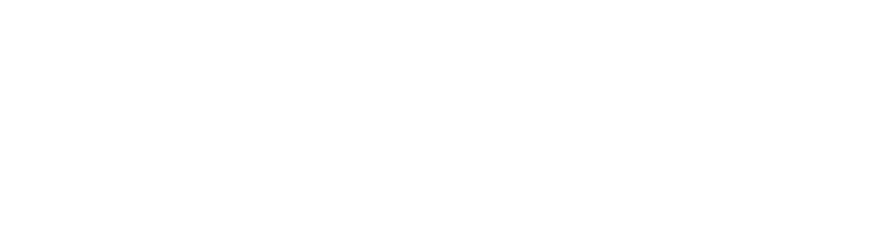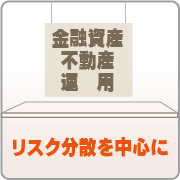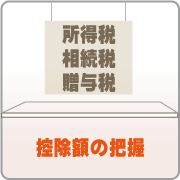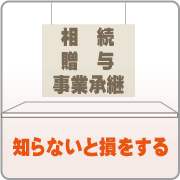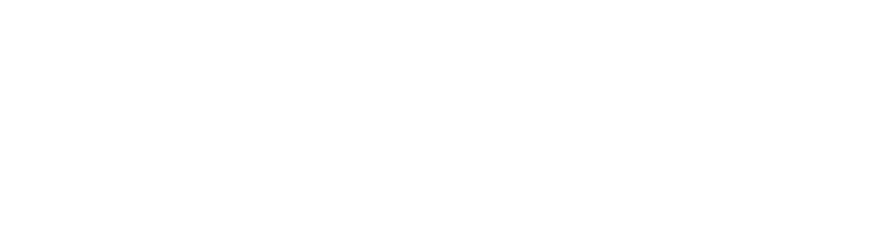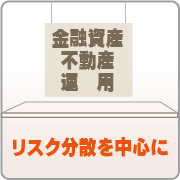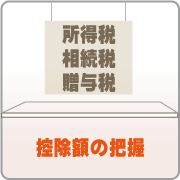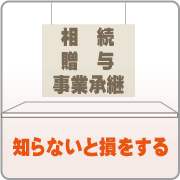◇関連法及びFP倫理規程により、特定保険会社の推薦は行っておりません。3社の見積もりを取るお手伝いをいたしております。
保険業法では、保険を生命保険固有分野(いわゆる第一分野の保険)、損害保険固有分野(いわゆる第二分野の保険)、生命保険・損害保険のどちらともいえない分野を第三分野の保険として、3つに大別しています。
1.第一分野の保険は「生命保険」のことで、人の生存または死亡に対して一定額の保険金を支払うことを約束するものであって、生命保険会社が引受ける保険です。
2.第二分野の保険は「損害保険」のことで、一定の偶然な事故によって生じる可能性がある損害に対して保険金を支払うことを約束するものであって、損害保険会社が引受ける保険です。
3.第三分野の保険は「傷害保険」や「医療保険」などのことで、ケガや病気またはケガを原因とする死亡などに対して保険金を支払うことを約束するものであって、生命保険会社または損害保険会社のいずれでも引受けることができる保険です。
一定額の保険金は「定額払い」と呼ばれており、あらかじめ契約時に定められた金額が保険金として支払われます。生命保険、傷害保険、医療保険などは、人の身体に値段をつけることはできないという考え方があり、こうした定額払いが基本となっています。
一方、一定の偶然な事故によって生じる可能性がある損害に対する保険金は「実損払い」と呼ばれており、損害によって被った金額が保険金として支払われます。損害保険は、損害により不当な利益を得ること(いわゆる焼け太り)を防ぐという考え方があり、こうした実損払いが基本となっています。
生命保険会社と損害保険会社は第一分野の保険と第二分野の保険を兼営することを認められていませんが、第三分野の保険はそれぞれ引受けることができます。
生命保険の種類
もしものアクシデントに備えるのが生命保険。しかし、どんな保険に、どのくらいの期間、いつ入っておけばよいのか、自分ではわからない人が多いものです。生命保険のしくみや種類、選び方などを・・・
もしものアクシデントに備えるのが生命保険です。しかし、どんな保険に、どのくらいの期間、いつ入っておけばよいのか、自分ではわからない人が多いものです。具体的にどのようなことを学ぶのかをご紹介しましょう。
もしもの死亡に備える生命保険
私たちの人生には、さまざまなリスクがあります。その中でも特に負担の大きい「死亡」に備えるのが生命保険です。
生命保険は、世帯主などが万が一亡くなったときに、残された家族が生活していくためのお金が給付される保険です。生命保険には複数の種類がありますが、主なものは以下の4つです。
1.定期保険
保険期間が一定で、保険期間中に死亡した場合に死亡保険金が受け取れるタイプの保険です。満期保険金はありません。保険期間中に死亡事故が起こらなければ、保険料を払って契約が終了しますので「掛け捨てタイプ」とも呼ばれます。
2.終身保険
保険期間が「終身」つまり一生涯続き、死亡した場合に死亡保険金が受け取れるタイプの保険です。満期保険金はありませんが、保険期間が生涯続くので、いずれは必ず死亡保険金を受け取ることになります。保険料の払い込みが一定年齢、または一定期間で満了する有期払い込みタイプと、一生涯払い続ける終身払い込みタイプがあります。
3.定期付終身保険
定期保険と終身保険を合わせたタイプの保険です。一定期間までは定期保険部分と終身保険部分の両方から死亡保険金が受け取れ、定期保険期間が終了すると、終身保険だけが残るしくみです。
4.養老保険
保険期間が一定で、その間に死亡した場合には死亡保険金が、満期時に生存していた場合には満期保険金が受け取れるタイプの保険です。死亡保険金と満期保険金は同額です。
生命保険の加入方法
一般的に、生命保険は結婚や出産のタイミングで加入する人が多いようです。必要保障額は、以下のように計算します。
必要保障額=「A.残された家族の人生に必要な金額」―「B.残された家族が受け取る収入・貯蓄」
A.残された家族の人生に必要な金額
【残された家族の生活費】
末子が独立するまでは現在の7割から8割、末子の独立後、配偶者が亡くなるまでは現在の5割から6割の金額として計算します。
【残された家族の住居費】
末子が独立するまでは現在と同額、末子の独立後、配偶者が亡くなるまでは現在の5割から6割の金額として計算します。
【残された子どもの教育費】
希望する進路に合わせて、現在から独立するまでに必要な金額を計算します。
【死亡整理金】
葬儀費用など
B.残された家族が受け取る収入・貯蓄
【残された家族の収入】
配偶者が働く場合などに得られる収入を計算します。
【死亡退職金】
受け取れると想定される金額
【年金】
残された配偶者が受け取る遺族年金や、老齢年金
【貯蓄】
現時点での貯蓄額
必要保障額は、常に同額ではありません。子どもが増えたとき、マイホーム購入時、子どもの独立時などには保障金額や内容を見直すのが理想的です。また、人生で叶えたいイベントや、希望する暮らしぶりによっても個人差があります。
そこで、前述した保険の種類を組み合わせる、もしくは保障額を変更することによって、家族の現状に合った保障を準備するようにしましょう。
生命保険は契約したままではNG
生命保険は家族のライフプランや資産の状況、働き方によって、生命保険はその都度見直すことが大切です。
生命保険は、契約したきりそのままにしている人も少なくありません。しかし実は、家族のライフプランや資産の状況、働き方によって、生命保険はその都度見直すことが大切です。
「生命保険は難しいし、考えるのは面倒」という方は少なくありません。とりあえず加入しておかなければ、と契約したきり長年そのままにしてしまっている、という方もいるのではないでしょうか。そのような方の多くは、加入している生命保険の内容や金額をすっかり忘れてしまっています。
しかし、生命保険は契約してからも、定期的に内容を確認したり、そのときの状況に合わせて見直したりすることが大切です。では、どのように見直すのが良いのでしょうか。
生命保険の見直しどき[1]
生命保険は、ご自身や家族のライフプランに合わせて見直すのが理想的です。それは人生のステージによって、必要な生命保険の保障額が異なるためです。これを「必要保障額」と呼びます。
一般的なライフプランでは、結婚するまでは大きな保障は必要ありません。ですから、生命保険はもしも自分が死亡したときに必要な葬儀費用程度があれば十分です。おおよそ、200万円から300万円の保障があるとよいでしょう。
結婚をして配偶者を扶養するようになると、必要保障額は大きくなります。自分が万が一死亡した後に、配偶者が生活するための費用や住居費なども含めて計算します。もし、万が一の際に配偶者が働くつもりなら、得られると想定される収入は差し引いて考えます。なお共働きの場合は、お互いに残したい金額が必要保障額といえます。
子どもが生まれると必要保障額はさらに大きくなります。子どもの教育費や生活費が増えるためです。一般的には、必要保障額にはまず葬儀費用などの死亡整理金として200万円~300万円を含めます。ここに、家族の生活費、住居費、教育費を加えて計算します。生活費としては、末子が独立するまでの期間は現在の生活費の7割程度を目安に計算します。末子の独立後、配偶者が一人で生活するための生活費としては、現在の生活費の5割程度を目安に計算します。
生命保険の見直しどき[2]
生命保険を必ず見直したいタイミングの一例が、マイホームの購入時です。と言うのも、賃貸とマイホーム購入とでは、必要保障額が変わってくるためです。
賃貸に住んでいる方なら、世帯主の死亡後も同じ部屋、もしくは別の部屋を借りるための家賃がかかります。ですから、必要保障額にも配偶者が生きている間(基本的には平均寿命まで)の家賃の金額を含めましょう。
ところが、マイホームを購入して、世帯主の名義で住宅ローンを借り入れると、多くの場合は団体信用生命保険に加入することになります。団体信用生命保険は、住宅ローンの名義人が万が一死亡すると、その時点での残債と同じ金額の保険金が下りるものです。ですから、その後のローン返済は不要になります。すると、それまでは生命保険の必要保障額に含めていた住居費分が不要になるのです。多くの場合、生命保険の保障額を大幅に下げることができます。ただ、余裕を持って必要保障額を見積もりたい方は、固定資産税や維持費分などを住居費として含めておきましょう。
このように、生命保険は、家族の人生の状況によって、適切な保障額が変化していきます。しかし保険に加入したままになっていると、保障額が現状に合っていないことも多いものです。
女性の妊娠と保険
保険は病気やけがをしたときの出費をカバーするためにも使えます。それが、医療保険や医療特約です。これらの保障を得るためには、健康に関する「告知」が必要です。FP資格では、保険に・・・
独身の方や女性のなかには、「まだ自分は元気だし、万が一の場合でも困る人はいないから保険は必要ない」と思っている人も少なくありません。しかし、保険は病気やけがをしたときの出費をカバーするためにも使えます。それが、医療保険や医療特約です。
これらの保障を得るためには、健康に関する「告知」が必要です。FP資格では、保険に加入する際に必要な「告知」についても学習します。具体的にご紹介しましょう。
保険の「告知」
生命保険に加入するときには、契約者または保険の対象となる被保険者は、過去の傷病歴、現在の健康状態、職業などについて、事実をありのまま告げる義務があります。これを「告知義務」といいます。
医療保険や医療特約も含め、生命保険は多数の人々が保険料を出しあって、病気やけが、万が一の死亡に見舞われた人を相互に保障しあう制度です。もしも、初めから健康状態の良くない人や危険度の高い職業に従事している人などが他の人と同じ条件で契約すると、負担する保険料に対して受け取る給付金や保険金が不公平になってしまいます。
そこで、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に回答するのが「告知」です。
告知によって加入の条件が決まる
生命保険の告知では、健康状態、かかったことのある傷病名、治療期間、職業などを回答します。ここで回答した内容に基づいて、生命保険に加入するための条件が決定します。傷病歴等がある場合、その内容や申込みをする保険商品によっては、通常どおり契約できない場合があります。その際には、保険料の割増や保険金の削減がされるか、「特定部位不担保」などの特別な条件がつきます。
「特定部位不担保」とは、身体の特定の部分に関する傷病を負った場合やそれが原因で入院などをした場合には、給付金や保険金を支払わないという条件です。「特定部位不担保」の条件が付く期間は、一定期間のこともありますし、保険期間中ずっと付くこともあります。
また告知の内容次第では、保険の契約ができないこともあります。このような方のために、健康状態や過去の傷病歴に関する告知が不要な生命保険や、傷病歴等があっても契約しやすい生命保険もあります。
妊娠すると保険に入れない!?
病気やけがをしたことがなく特殊な職業についていない方は、基本的に加入に際して特に条件はつきません。
しかしながら、女性の場合には油断は禁物です。妊娠すると、契約にあたって条件が付くことや契約ができないこともあるのです。また、大きな病気やけがではなくても、体調を崩すなどの理由で病院にかかった直後だと、保険の契約上は条件が付くことがあります。
「今は元気だから保険は必要ない」と思って保険に加入しないままにしていると、いざというときに希望通りの条件で保険の契約ができなくなってしまうことがあります。
早めにご自身やご家族のアクシデントに備えてみてはいかがでしょうか。
損害保険の仕組み
損害保険は、補償タイプと積立タイプがあります。後者は、満期まで契約が存続した場合、積立部分に該当する額と予定利率での運用部分を合計した満期返戻金が支払われます。また、運用利回りが予定利率を超えたときは、配当金が支払われます。
なお、積立タイプの保険を途中で解約すると、解約返戻金が支払われますが、通常その額はそれまでに支払った保険料の総額より少なくなります(契約後、短期間で解約した場合の解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかとなります)。
保険料の決まり方
保険料の決まり方ですが、考え方は生命保険と同じです。たとえば、自動車保険の場合、過去の統計などをもとに、年齢別の自動車事故件数を予測し、将来の保険金などの支払いにあてるための必要額を算定し、また、事業運営に必要な経費をあらかじめ見込み、保険料を算定するといった具合です。
保険金の算定方法
火災保険などモノを対象とする保険では、契約金額を保険の対象となるモノの時価と同額に設定していれば、損害額の全額が支払われます。契約金額が時価に満たない場合は、その契約金額を限度に以下の算式で保険金が決定されます。
保険金=損害額×契約金額/時価
時価:同等のモノを新たに建てたり購入するための費用から使用による消耗分を差引いた額
契約金額:受取る保険金の限度額
なお、建物を対象としている火災保険などは、契約金額が時価の一定割合以上であれば、契約金額を限度に実際の損害額が支払われます。また、通常の火災保険では、「時価」をもとに契約金額を設定しているため、これだけでは同じ建物を建て直すコストを全額カバーできません。
保険金だけで同じ建物を建て直したいというニーズがある方は、契約時点でその家を新築した場合にかかるコストを算定した「再調達価額」をもとに契約金額を設定することもできます。再調達価額は当然時価を上回りますので、その分保険料は割高となります。
損害保険の種類
損害保険には、火災、自然災害、自動車事故、レジャー中の損害、医療費や介護費用などさまざまなリスクを補償する商品があります。
また、生命保険と同様に、保険期間が長期におよぶ商品や貯蓄機能をもった積立型商品もあります。ライフスタイルの多様化に伴って、損害を補償するその対象も多様化・複雑化しています。
火災保険・地震保険のポイント
まず火災保険で補償してほしい対象は「建物」だけでいいのか「家財」だけでいいのか、それとも「建物と家財」の両方を補償してほしいのか、最初はこの3つのパターンで考えてみましょう。一般的には両方を補償するタイプのプランに加入される方が多くなっています。
次に補償範囲を確認しましょう。火災保険では火災以外にも様々な損害に対して補償を受けることができますが、必要がないと思われるものを外すことによって、保険料を安く抑えることができるのです。
火災、落雷、台風、竜巻、洪水、雪災、雹災
水漏れ、雨漏り、破裂・爆発、盗難・空き巣
物体の落下・飛来・衝突、不測かつ突発的な事故(破損)
騒擾・集団行動に伴う暴力行為や破壊行為
地震保険は単独では契約できません。火災保険に付帯する形で契約します。
補償内容は、地震・噴火・津波が対象で、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で任意に定めます。上限は、建物が5,000万円、家財は1,000万円が上限です。
支払われる保険金額は、
全損:100%(時価を限度)
半損:50%(時価の50%を限度)
一部損:5%(時価の5%を限度)
保険料は、所在地と建物の免振・耐震性能、築年数によって決まります。
自動車保険のポイント
最近の自動車保険には注目したいさまざまなポイントがあります。いくつかご紹介しましょう。
◇人身傷害補償保険
契約した自動車またはほかの自動車に乗車中や歩行中に、自動車事故で死傷したり後遺障がいを被った場合に、自分の過失部分を含めて、自分の契約している損害保険会社から損害額の全額について保険金が支払われます。
◇示談交渉サービス
自動車事故の損害についてどのような賠償をするのか、その具体的な内容を保険会社が被保険者に代わって、被害者と直接示談交渉をしてくれるサービスです。
たとえば、事故についての損害を加害者と被害者が公平に分担するために、被害者にも過失(不注意)がある場合、加害者の損害賠償を被害者の過失に応じて減額する過失相殺の仕組みがありますが、これも示談交渉サービスで対応してくれます。このサービスは現在の任意保険に含まれていることが普通で、人身事故ではほとんどが保険会社が直接交渉相手となります。
◇満期案内サービス
つい忘れがちな保険の満期日を電話や電子メールなどで知らせてくれるサービスです。このサービスを実施している代理店に対して登録することでサービスが受けられます。
◇代車費用担保特約
自動車事故で車を修理する間、代車費用を補償してくれる特約です。
◇弁護士費用担保特約
自動車事故で人身被害事故を被ったとき、相手との交渉を弁護士に依頼した場合の弁護士費用を補償する特約です。
◇ロードサービス
事故、故障を問わず自力走行不能となった場合のレッカーけん引サービスやバッテリー上がりなどのトラブルに対する緊急修理サービス等を提供します。
その他の損害・賠償保険
普通傷害保険・家族傷害保険
交通事故傷害保険・ファミリー交通障害保険
国内旅行傷害保険・海外旅行傷害保険
所得補償保険・介護費用保険
ゴルファー保険
個人賠償責任保険・生産物賠償責任保険
会社役員賠償責任保険
労働災害総合保険・請負業者賠償責任保険
施設倍賞責任保険
これらのサービスは保険会社によって異なります。また特約は任意でつけられます。よく検討して賢く活用しましょう。