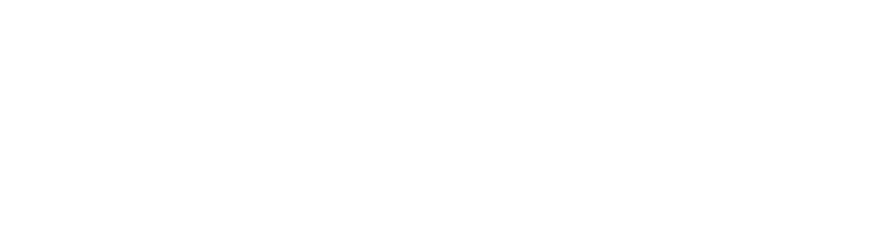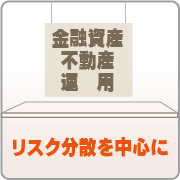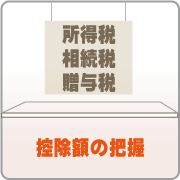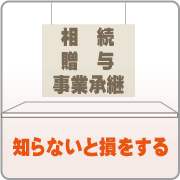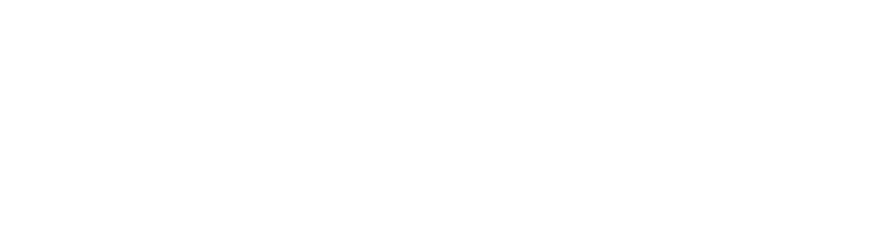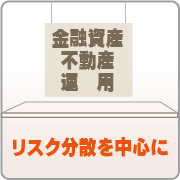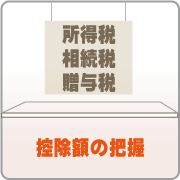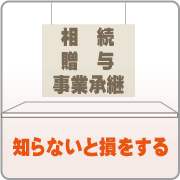遺言書の種類
普通方式の遺言書には以下の3種類があります。
1.自筆証書遺言:遺言者本人だけで作成。最も簡単な遺言書。
2.公正証書遺言:公証役場で公正証書として作成される遺言書。作成には遺言者以外に二人以上の証人が必要。このほほうだけ、開封時に家庭裁判所の検認手続きが不要です。
3.秘密証書遺言:遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場へ行き、遺言書の封印を行う。
相続放棄と限定承認
相続放棄の申述
1. 申述人:原則として相続人が申請
2. 申請機関:原則として相続が開始してから3ヶ月以内に申請
3. 必要書類:
・ 相続放棄申述書
・ 被相続人の住民票の除票
・ 戸籍謄本
・ 他、事案によって追加書類がある
4. 申請先:亡くなった人(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所
5. 費用:申立人1人につき収入印紙800円分
相続の限定承認の申述
1. 概要:
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
(1)相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
(2)相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
(3)被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,(2)の相続放棄又は(3)の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
限定承認の場合は以下です。
2. 申述人:相続人全員が共同して行う必要があります。
3. 申述期間:申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
4. 申述先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
相続と贈与をうまく行う
宅地・建物の相続、相続発生前3年間の贈与などの税金対策が重要です。
【相続時精算課税制度】
1 制度の概要
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
2 適用対象者
贈与者は贈与をした年の1月1日においてて60歳以上の親又は祖父母、受贈者は贈与者の推定相続人である贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子または孫とされています。
3 適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
事業承継設計の手順
事業承継設計(自社株対策)は、以下のようなステップで行います。
1.自社株評価及び他の相続財産の評価と予想相続税額の算出
2.自社株及び他の財産の分割をある程度決め、各人ごとの予想相続税額の算出
3.各人ごとの納税資金の検討
4.株価準備
自社株の評価を下げることにより後継者への引継ぎコストを抑え、引継ぎをスムーズに行えるようにする。
○類似業種比準価額の引き下げ
○純資産価額の引き下げ
○会社規模区分の変更
○特定会社に該当しないようにする
5.株数準備
株価準備を実行して自社株の評価を引き下げても、業績の良い会社であれば再び株価は上昇していく。そこで、オーナー社長の相続税を低くするには、ある程度自社株を生前に移転していく必要があります。
6.納税準備
納税準備にはいくつかの方法があります。
○役員退職金等の活用
○生命保険の加入
○相続財産の売却
○会社自身が自己株式を取得
○自社株の物納
○株式公開
【取引相場のない自社株の評価】
取引相場のない株式の評価は、株式の取得者が会社に対する経営支配権を有するかどうかによってその評価方式が異なります。
経営支配権を有する者が取得した株式については、評価する会社の規模区分に応じて、「類似業種比準方式」、「純資産額方式」及びその併用方式があり、
評価する会社の規模区分によって異なってきます。
経営支配権がないものが取得した株式については、原則として会社の規模区分とは関係なく会社の配当実績により「配当還元方式」で評価します。