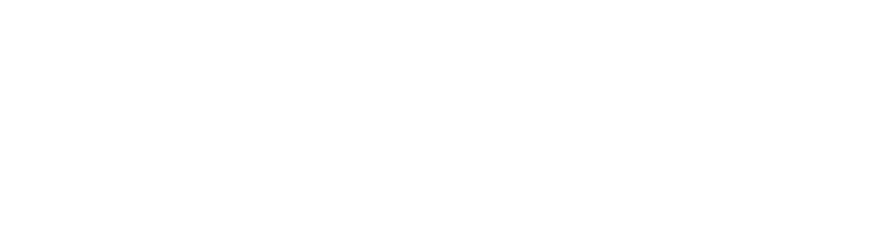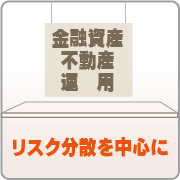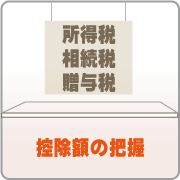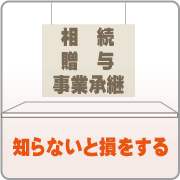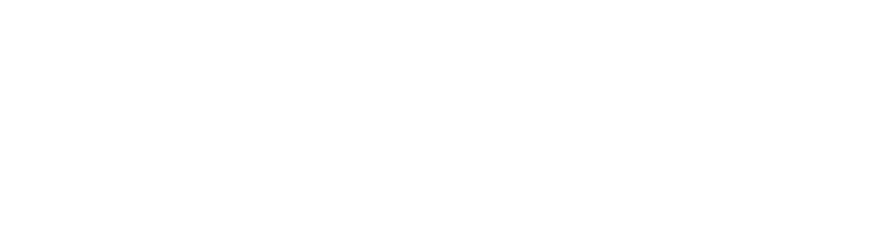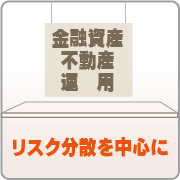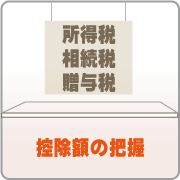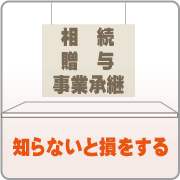◇将来の相続に備える相続設計
相続設計には大きな4つの柱があり、それぞれの方法と効果が異なるので、どれか一つに偏ることなくバランスよく組み合わせることが大切です。
1.相続税評価の引き下げ
【賃貸用不動産の購入・建築】
賃貸の用に供する土地・建物は、一定の割合で評価額が減額されます。
a) 土地の場合:自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
b) 建物の場合:固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
【土地利用形態の変更】
土地の評価をする場合、1本の路線に面する土地より2本の路線に面する土地のほうが利用価値が高いため、相続税評価額は高くなります。
そのような場合、二方路線の影響を受けないよう土地を分割し、それぞれ別の相続人が取得すると評価を下げることができる場合もあります。
【小規模住宅地等の評価額の特例の活用】】
被相続人の主な財産が自宅や事業用資産で、その敷地の相続税評価額が高額である場合は、多額の相続税がかかってしまい、手元資金では相続税を
支払いきれず、相続財産を売却しなければならないことも考えられます。
そこで、最小限の居住または事業の場の確保を図るために、これらの土地の評価額から一定額を減額して課税価格を計算し、相続税を軽減する
特例が設けられています。減額割合は、
特定居住用宅地等:330㎡まで、80%
特定事業用宅地等:400㎡まで、80%
貸付事業用宅地等:200㎡まで、50%
2.贈与等によりる財産の移転
生前に財産を相続人に移転し、被相続人の課税資産の総額を減らす方法もあります。
【配偶者に対する贈与税の特例の活用】
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合は、その贈与を受けた
財産の価格から贈与税の基礎控除額110万円とは別に2,000万円まで控除することが可能です。
【相続時精算課税の特例の活用】
本制度を選択した場合の相続税は、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産と合算し、贈与時に納めた贈与税相当分が
相続税から控除されます。
【直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税】
父母、祖父母から20歳以上の子・孫(合計所得金額2,000万円以下)への住宅の購入や増改築の資金は、床面積240㎡以下に対し
500万円まで非課税(省エネ・耐震住宅は+500万円)となります。)
【賃貸建物の売買または贈与】
賃貸建物を早期に売買または贈与することにより、推定相続人はその後受け取る賃料収入を将来の相続税の資金として確保することが可能になります。
3.納税資金の確保(物納の活用)
地価が上昇しているときは不動産を売却して納税資金を確保できるが、地価が下落しデフレ傾向の時は物納制度が有効です。
4.遺産分割と財産の分析
被相続人の思い通りに財産を分割するには、財産をあらかじめ分析しておくことが必要です。
【将来承継する資産】
■承継する不動産(守る、残す不動産)
■有効活用する不動産
【将来なくなる資産】
■納税財源としての不動産(貸宅地・物納不適格財産の物納整備)
■売却換金用の不動産(事業用資産の買い替え、金融資産、生命保険へ資産の組替え)