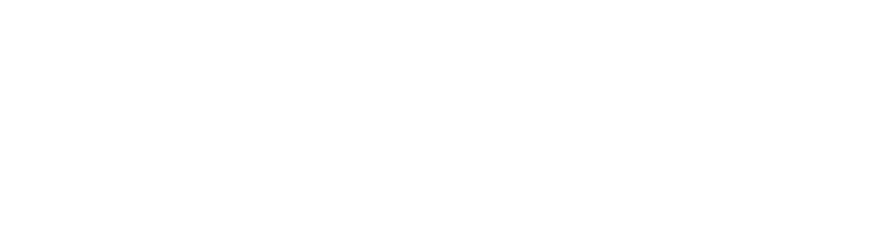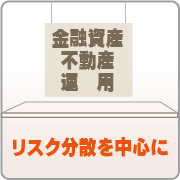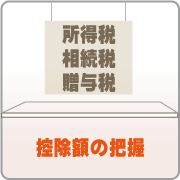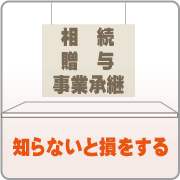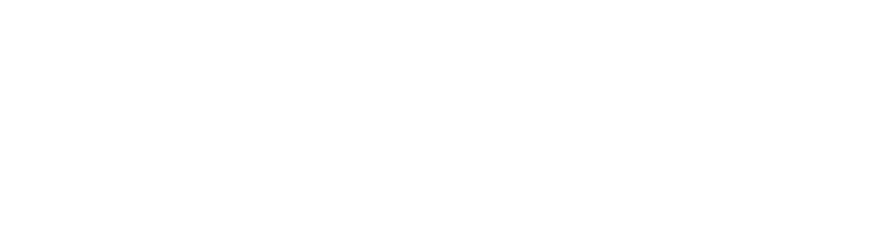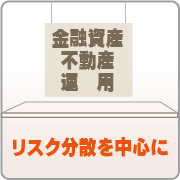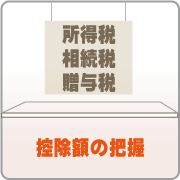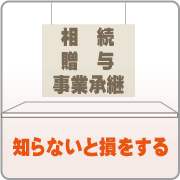◇株式以外の金融商品、即ち投資信託・REIT・国内債券・外国債券・外国為替(FX)・金・銀・白金・大豆・小豆・トウモロコシ・綿糸、日経225等先物についてもご要望があれば取引方法及びリスクについてご説明いたします。
但し、関連法及びFP倫理規程により、個別商品の投資助言及び特定証券会社の推薦は行っておりません。
投資対象の選び方
どの金融商品を使って投資をするかは、資産の状況や将来のライフプラン、また投資に対する価値観によって一人ひとり異なります。
結婚や出産、マイホームの購入、子どもの教育や老後の生活などのライフイベントを予定しているのかどうか、またそれはいつなのか、
どれくらいの資金をかけたいか、などを考えてみましょう。すると、「何年後にいくら用意すればよいか?」という投資の目標が見えてきます。
その目標に合わせて、金融商品を選びましょう。
自分に向いている投資方法を知る
適切な投資には、自身のリスク許容度や資産の状況をかんがみた「ポートフォリオ」を把握することが大切です。
投資を始めてみようと思ったときに疑問に思うのが、「いくらくらい投資すればよい?」「どれくらいリスクのあるものなら買ってもいいの?」ということです。適切な投資をするためには、自身のリスク許容度や資産の状況をかんがみた「ポートフォリオ」を把握することが大切。
ここでは、その一部をご紹介しましょう。
自分に向いている投資方法を知るための「リスク許容度」
「投資」というと、「お金を儲けること」というイメージを持つ人もいるでしょう。そのような人は投資を始めるときに、絶対儲かる方法を探そうとするかもしれません。
しかし残念ながら、投資において絶対に儲かる方法はありません。投資は、自分に合った方法で、無理なく、自分の希望する成果を目指すことが大切です。それを見極めるために重要なのが、自分の「リスク許容度」を把握することです。
「リスク許容度」とは、投資をするにあたってどれくらいの大きさのリスクであれば投資家が許容できるか、という度合いのことです。
たとえば100万円を投資するとき、ある人はそのうち10万円くらいであれば仮に損失を出したとしても構わない、と考えるでしょう。そのような人は、元本に対しておおよそ1割の範囲内で値動きをする金融商品であれば、投資対象として選択できます。
しかし、なかには1円たりとも損失を出したくない、と考える人もいます。そのような人は、値動きのある金融商品に投資することはできません。このように、取れるリスクの大きさには個人差があるのです。
リスク許容度は投資する人の性格や価値観によっても左右されますが、適切な投資方法を見極めるためには、他にもさまざまな要因を考慮しておくことが大切です。投資する人の年齢や投資期間、収入、保有資産(余裕資産)の規模、投資経験や運用知識なども、投資対象や金額を決定する重要な要素になります。
「ポートフォリオ」は、いわば自分に最適な運用メニューということです。
分散投資
自分のリスク許容度を判断し、どれくらいリスクを取れるかを把握できたら、投資に充てられる金額や具体的な金融商品を決定します。投資ではひとつの金融商品だけに集中するよりも、複数の金融商品を組み合わせるのが効果的です。この組み合わせのことを「ポートフォリオ」といいます。
「ポートフォリオ」には、預貯金、株式、債券、投資信託、REIT、外貨預金、外国株式、金など、複数の異なる金融商品を組み入れるのが理想です。これを「分散投資」と呼びます。
異なる金融商品を組み合わせると、リスクとリターンの特徴が異なる資産を保有することができます。するとある資産が損失を被っても、別の資産は利益を出すことができますから、さまざまなリスクに対応しながら安定した資産運用ができるようになります。
この「ポートフォリオ」に組み入れるべき金融商品は、個人のリスク許容度に応じて異なります。自分のリスク許容度を把握し、それに見合った金融商品を組み入れていけば、最適なポートフォリオ、すなわち、成功につながる自分だけの運用メニューが完成することでしょう。
※投資は自らの責任において行うものです。必ずしも期待通りの結果が得られるものではなく、損失が生じる場合もありますのでご了承ください。
NISA、株式投資のポイント
NISA(ニーサ)は小額投資者のための非課税制度で、利益に対する所得税・住民税が非課税になるというしくみですが、元本保証でもなく、通常の株式取引と同様で、銘柄次第で損をすることを忘れてはいけません。「簡単に誰でも取引できそう」という考えは間違いです。株式投資の一般的なポイントは以下の通りです。
株式投資が初めての人にはどのように銘柄を選べばよいのか、どのように購入すればよいのか、わからないこともたくさんあることでしょう。
NISAのスタートとともに注目を集めている株式投資。でも、初めての人にはどのように銘柄を選べばよいのか、どのように購入すればよいのか、わからないこともたくさんあることでしょう。
投資は余裕資金で行うのが大原則
初めて投資をするときには、張り切って大金を充てようとする人もいます。ビギナーズラックで利益を出せる人もいますが、株式は値動きのある金融商品なので必ずしもいつも成功するとは限りません。
また場合によっては投資先の企業が倒産するなどにより、株式の価値がゼロになってしまうリスクもあります。
ですから、投資は余裕資金で行うことが大原則です。余裕資金とは、万が一投資した金額がゼロになったとしても、生活に支障が出ない程度の金額です。投資成績がマイナスとなる事態も想定し、家計に大きく影響しない範囲内の金額で行いましょう。
投資の成功には「分散」が大切
投資によるリスクを軽減するためには、分散投資が有効です。分散投資の方法にはいくつかありますが、おもに次の2つがあります。
銘柄分散
ひとつの銘柄に集中して投資するのではなく、値動きの異なる複数の銘柄に分けて投資をすること。ひとつの銘柄が値下がりしても、他方の銘柄が値上がりしていれば資産全体の価値が下がらないので、値下がりのリスクを軽減することができます。
時間分散
投資のタイミングをずらすこと。積立などで定期的に一定額を投資すると、購入額が毎回異なります。すると、一時的な価格変動によって値下がりするリスクを分散させる効果が期待できます。
良い銘柄に出逢うためには株式を分析するのも有効
株価の上昇が期待できる銘柄を見つけるために、成長性や安定性を分析することも重要です。このためには、株価動向を分析するテクニカル分析や、企業の財務内容などを分析するファンダメンタル分析を行います。
テクニカル分析とは、株価の推移を表したグラフである「チャート」の動きを分析して、株式の売り時や買い時を判断する方法です。テクニカル分析には、大きく分けて「トレンド系」と「オシレーター系」の2つがあります。
トレンド系
株価の方向性を示す指標です。株価がこれから上昇するのか、下落するのかを推測するために用いられます。「ローソク足」、「移動平均線」、「ボリンジャーバンド」などがあります。
オシレーター系
株式を買う人が多いか、売る人が多いかといった相場の勢いを示す指標です。「MACD」、「RSI」、「ストキャスティックス」などがあります。
このように株式投資で成功するためには、リスクを軽減するための知識や株価の動向を推測するための知識が必要です。ファイナンシャルプランナー資格の勉強をすれば、これらについてより深く理解できます。学習で得た知識を活かして、株式投資に挑戦してみてはいかがでしょうか。
※投資は自らの責任において行うものです。必ずしも期待通りの結果が得られるものではなく、損失が生じる場合もありますのでご理解ください。
金融機関破たん時の資産保護
さまざまな形で金融機関を利用するときには、その金融機関が破たんしたらどうなる?ということが気になる人もいるでしょう。私たちの資産はどのように守られるのでしょうか。
銀行に預金をする、証券会社で株式や投資信託を購入する、保険会社で保険の契約をする……。さまざまな形で金融機関を利用するときには、その金融機関が破たんしたらどうなる?ということが気になる人もいるでしょう。
日本では、そんなまさかの事態に私たちの資産を守るセーフティネットのしくみがあります。では私たちの資産はどのように守られるのでしょうか。
「預金保険制度」による銀行預金保護
日本には、銀行や証券会社、保険会社などの金融機関が破たんしたときに、顧客の資産を守るセーフティネットがあります。そのしくみは、銀行などの預金、証券会社の株式や投資信託、保険会社の保険契約によって異なります。
預金を取り扱う金融機関は、預金保険制度に加入することが義務付けられています。預金保険制度は預金保険機構が運営し、下記の金融機関が加入しています。
・日本国内に本店がある銀行
・信用金庫、信金中央金庫
・信用組合、全国信用協同組合連合会
・労働金庫、労働金庫連合会
・商工組合中央金庫
なお上記の金融機関であっても、海外にある支店、外国の銀行の日本支店などは対象になりません。
預金保険制度に加入している金融機関に資産を預けると、預金保険法という法律によって自動的に保険がかけられます。このため万が一預け先の金融機関が破たんして、預金などを引き出すことができなくなった場合には、預金保険機構が預金者を保護します。保護する方法には、「預金者に保険金を支払う」、「破たんした金融機関を合併などによって救済する金融機関が現れた場合には、その救済金融機関に資金を援助する」という2つがあります。
預金保険制度の対象になる金融商品は、以下の通りです。
全額保護されるもの
当座預金、利息の付かない普通預金
金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円と破たん日までの利息
利息の付く普通預金、定期預金、元本補てん契約のある金銭信託など
但し、外貨預金や他人名義の預金などは保護されません。
株式や投資信託は分別保管されています。
証券会社などで運用している株式や金銭などは、証券会社自身の財産と分けて保管することになっています。これを「分別保管」といいます。ですから、もし証券会社が破たんしても資産は顧客に戻ってきます。しかし万が一、何らかの事情で証券会社が顧客に資産を返還できなくなった場合に備えて、「投資者保護基金」による補償制度もあります。
投資者保護基金では、1人当たり1,000万円までの資産を補償します。1,000万円を超える部分は、証券会社が破たんしたときの状況によって一部カットされることがあります。
対象になる金融商品は、株式、投資信託、債券などです。外国為替証拠金取引などの店頭デリバティブ取引や外国市場デリバティブ取引は対象になりません。
「保険契約者保護機構」による保険保護
保険会社が破たんした場合には、保険の契約者は「保険契約者保護機構」というしくみで保護されます。破たんした保険会社の保険契約は、救済する保険会社が現れた場合にはその保険会社、現れなかった場合には保険契約者保護機構などが引き継ぎます。ですから、契約している保険はそのまま継続することができます。
保険契約の引き継ぎが行われるときには、「責任準備金」という将来の保険金等の支払いに備えた積立金の削減、もしくは予定利率の引き下げなど、契約条件の変更が行われることがあります。ただし、責任準備金のうち、原則として90%までは補償されます。
投資信託を選ぶときのチェックポイント
・純資産残高
残高が少ないと十分な運用ができず、一定金額を下回ると運用をやめて投資信託の資産を保有者に返還する「繰上償還」を行うことがあります(繰上償還する残高の目安は各投資信託の投資信託説明書(目論見書)で確認できます)。
・残高の推移
現在の残高は十分でも、以前より減ってきている投資信託は、資金が流出していて十分な運用ができなくなっている可能性があります。
・運用期間
新しい投資信託は運用の良し悪しを判断できないので、できれば3年以上運用されているものの中から選びましょう。
また、運用期間が“無期限”ならOKですが、期間がいつまでと決められている投資信託は、それが自分が保有しようとしている期間より長いかどうかをチェックしてください。
このように、金融商品にはその種類に応じて個人の資産を守るためのセーフティネットがあります。そのしくみを知っていれば、自分の資産を運用する際にも安心です。FP資格の学習をして、資産を守る方法をしっかり理解すると良いでしょう。