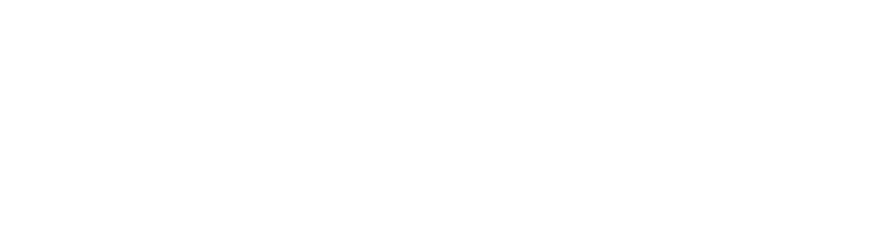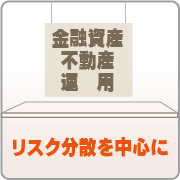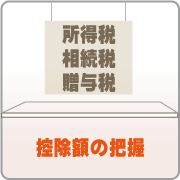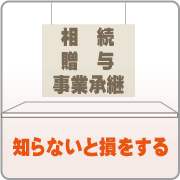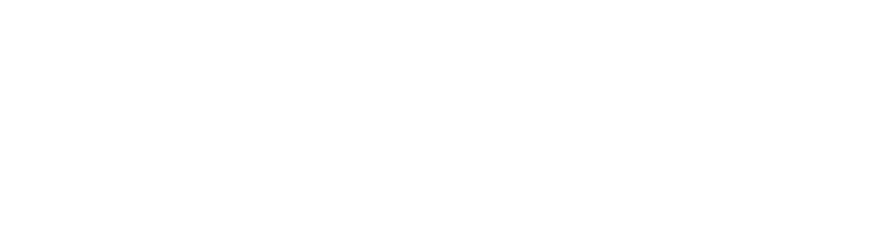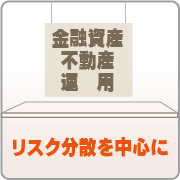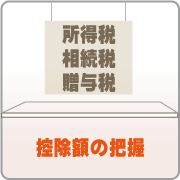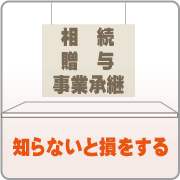◇関連法及びFP倫理規程により、各種手続き書類の代理作成は行っておりません。
企業型確定拠出年金の概要
企業型確定拠出年金は、以下のような制度です。
会社が毎月掛金を従業員の個人別専用口座に拠出します。
会社の用意した運用商品の中から従業員(加入者)が運用商品を選択します。
原則60歳になったら専用口座から引き出して年金または一時金として受け取ることができます。
個人型確定拠出年金制度の概要
自分の年金資産についての運用方法は、加入者個人で決めることができます。
加入者ご本人が運用商品を選択します。
原則60歳から老齢給付金を受け取ることができます。
年金・一時金いずれかから選択することができます。
制度の特徴
掛金が所得控除され、所得税や住民税が軽減するなどの税制上の優遇措置があります。
掛金全額が所得控除※の対象
掛金については制度の概要へ
運用により得られた利益は非課税
受給時も退職所得控除や公的年金等控除の対象
(平成24年10月1日現在)
離転職しても積み立てた年金資産を持ち運ぶことができます。
(ポータビリティ)
確定拠出年金では、転職・離職の際にそれまで積み立てた年金資産を持ち運ぶことができます。
実施主体:国民年金基金連合会
加入できる者:1.自営業者等(農業者年金の被保険者の方、国民年金の保険料を免除されている方を除く)(国民年金第1号被保険者)
2.企業型年金加入者、厚生年金基金等(注)の加入員等の対象となっていない企業の従業員(国民年金第2号被保険者)
掛金の拠出:加入者個人が拠出(企業は拠出できない)
拠出限度額:1.自営業者等68,000円(月額)
※ 国民年金基金の限度額と枠を共有
2.企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合23,000円(月額)
公的年金のしくみ
転職すると、加入する公的年金の種類が変わることがあります。具体的な内容をご紹介しましょう。
日本の公的年金には、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。公的年金は、働き方により加入する年金制度が3種類あります。
1.国民年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金です。老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があり、働き方によって被保険者の区分が異なります。
第1号被保険者
自営業者、フリーランス、学生、フリーター、無職の人など。国民年金保険料を自分で納めます。
第2号被保険者
厚生年金保険に加入している会社員など。厚生年金に加入する人は、自動的に国民年金にも加入することになります。
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人、いわゆる専業主婦の人。国民年金の保険料は、配偶者である第2号被保険者が加入する年金制度で納めます。ただし、年間収入が130万円以上ある人は、第1号被保険者となります。
2.厚生年金
厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人が加入する年金です。上記の通り、国民年金の第2号被保険者に分類され、厚生年金に加入すると国民年金にも加入することになります。給付を受ける時は、国民年金から支給される「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることになります。
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれ、保険料は勤務先と折半します。ですから、自己負担は保険料の半額になります。自己負担する保険料は、給与天引きで納付するのが一般的です。
3.共済年金
国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などが加入する年金です。厚生年金と同様に、第2号被保険者に分類され、共済年金に加入すると国民年金にも加入することになります。保険料の納付も、厚生年金と類似したしくみになっており、勤務先と折半します。給付を受ける時は、国民年金から支給される「基礎年金」に加えて、「共済年金」を受けることになります。
転職と年金
学生が就職をすると、第1号被保険者から第2号被保険者に変わることになります。このときは、就職先で年金の変更手続きをしてくれます。自分の年金手帳など、国民年金の基礎年金番号がわかるものを用意すれば、他には自分で手続きをする必要はありません。
会社員などが転職や出向などで勤務先が変わる時は、厚生年金から厚生年金、厚生年金から共済年金、共済年金から共済年金のいずれかに変わることになります。年金の管理・運用をする場所が変わりますから手続きが必要ですが、この場合の変更の手続きは新しい勤務先がしてくれます。
会社員が退職をした、独立をして自営業になった、などの場合は、第2号被保険者から第1号被保険者に変わることになります。細かい状況によって異なりますが、基本的には自分で第1号被保険者への変更手続きをする必要があります。
退職後に再就職をせず、かつ第2号被保険者(配偶者)の被扶養者にならない場合には、自分で第1号被保険者になります。
退職後にしばらくして再就職をする場合には、その時期によっては新しい勤務先で手続きをします。
退職をして、第2号被保険者の被扶養者になる場合は、第3号被保険者になります。この場合は、第2号被保険者の勤務先で変更の手続きをします。
このように、就職、転職や退職などの人生の節目には年金の切り替えも必要です。
老後のために必要な資金
高齢化が進むとともに老後の資金の準備が大きな課題に。
長寿を誇る日本では、高齢化が進むとともに老後の資金の準備が大きな課題になっています。定年の延長や再雇用の促進が広まる一方で、若い人の間でも老後の貯蓄や生活費を心配する人が増えています。
ゆとりある老後には毎月37万円が必要
平均寿命の伸びとともに、日本人の老後の生活は長くなりました。また、雇用形態や退職金制度の変化などによって、リタイア後の生活費を自助努力で備える必要性が高まってきました。ですから、現役の間から、老後資金を計画的に準備しておくことが大切です。
生命保険文化センター「生活保障に関する調査」によると、「ゆとりある老後生活費」は月額で平均35.4 万円となっています。これは、夫婦2人で老後生活を送る上で必要と考えられている最低日常生活費の平均月額22.0万円経済的にゆとりのある老後生活を送るための費用として、老後の最低日常生活費以外に必要と考えられている平均月額13.4 万円を合計したものです。ゆとりある老後生活費とは、「旅行やレジャー、趣味や教養、日常生活費の充実、身内との付き合い、耐久消費財の買い替え」などにかかる費用です。
老後に必要な病気・けが・介護への備え
日常生活や旅行、趣味などにかかる費用のほかにも、老後の生活で考慮しておきたいのが、病気やけが、介護が必要になったときなどにかかる費用です。老後は、若いときよりも体力や筋力が衰えるため、このようなリスクが高まります。
病気やけがで入院したときには、平均で約20万円の自己負担が必要と考えられています。
(「入院経験がある人のうち、高額療養費制度を利用した人及び利用しなかった人(適用外含む)の直近の入院時自己負担費用の平均は22.7 万円」)
また、介護が必要な状態になったときには、公的介護保険の範囲外の初期費用として約260万円、月々約17万円が必要と考えられています。
(「世帯主または配偶者が要介護状態となった場合の、公的介護保険の範囲外の費用に対して必要と考える初期費用の平均は262万円」「月々の費用の平均は17.2万円」)
ですから、これらのリスクに備えて、200万円~300万円は用意しておきたいものです。
老後の生活やリスクに備えて、リタイアまでに用意しておきたい金額の目安は、夫婦2人で約3,000万円といわれています。細かい金額は、年金の受取金額や退職金の有無、金額によって個人差があります。
老後には計画的な貯蓄が大切
老後の資金を準備するためには、比較的安全性の高い金融商品が向いています。たとえば、個人年金、個人向け国債、公社債投資信託などです。これらの金融商品は、比較的少額から購入することができ、定期的に積み立てることができる商品もあります。余裕資金の中から、一部を老後資金として運用すると、安心してリタイアを迎えることができるでしょう。
※投資は自らの責任において行うものです。必ずしも期待通りの結果が得られるものではなく、損失が生じる場合もありますのでご了承ください。
公的介護保険制度のしくみ
若い世代の方はまだまだ、介護と聞いてもいま一つ自分のこととしてイメージがわかないものです。老後のリスクの一つが、介護です。高齢化が深刻な問題になっている日本では、介護状態で長い老後生活を送る人も少なくありません。
しかし、若い世代の方はまだまだ、介護と聞いてもいま一つ自分のこととしてイメージがわかないものです。
公的介護保険は、介護保険料を支払った人が所定の状態になると介護サービスを受けることができる制度です。
公的介護保険には、40歳以上の人が加入します。40~64歳の医療保険加入者は第2号被保険者、65歳以上の人は第1号被保険者と区分されます。保険料は、第2号被保険者は公的医療保険(健康保険など)の保険料とともに徴収、第1号被保険者は年金からの天引きにより徴収されます。
介護保険サービスを受けられる基準は、被保険者の区分によって異なります。65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず要支援・要介護状態となったときに受けられます。これに対して、40~64歳の第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、受けることができます。
介護サービスの受け方
介護サービスを受けるには、市町村の窓口で所定の手続きを経て、介護状態の認定を受ける必要があります。介護状態は、日常生活の自立度について、要支援1,2、要介護1~5の区分で判断されます。この認定によって、受けられるサービス内容も変わります。
寝たきりや認知症で介護サービスが必要な方は要介護1~5と認定され、「介護給付」を受けられます。「介護給付」は自立して生活できない方に介護によるサポートをするものです。
今のところ要介護状態ではないものの、将来要介護状態になるおそれがあり生活に支援が必要な方は、要支援1,2と認定され「予防給付」を受けられます。「予防給付」は、介護の予防を目指すサービスです。
要介護、要支援に該当しないものの、今後、要支援・要介護になるおそれのある方も、居住している市町村によって実情に応じたサービスを受けることができます。
介護サービスの内容
介護保険サービスの内容は、おもに以下の5種類があります。
訪問介護、訪問看護などの「訪問系サービス」、通所介護、通所リハビリテーションなどの「通所系サービス」、短期間施設に入所する「短期滞在系サービス」、有料老人ホームなど、特定の状態にある方向けの住宅に居住する「居住系サービス」、特別養護老人ホームなどの介護施設に入所する「入所系サービス」です。
具体的にどのような介護サービスを受けるかは、要介護認定を得たのちに作成される「ケアプラン」によって決定します。サービスを利用すると、その料金のうち1割を自己負担します(要介護状態の認定に応じた支給限度額まで)。支給限度額を超えたサービス費用や、居住費、食費、日常生活費などは基本的に全額自己負担です。
ひとくちで「介護」といっても、元気なうちはなかなかイメージがわきづらいものでしょう。実際に介護が必要な状態になると、自立度に応じて細かい認定がなされ、受けるサービスの計画が立てられていくのです。
マイホームと住宅ローン
マイホームが欲しいと思っていても、「いつ買うべきか?」「いくらまでなら買えるのか?」なかなかわからないもの。状況に応じたマイホームの買い方や、住宅ローンの組み方など・・・
マイホームの購入は、人生の3大支出のひとつです。「いつかは欲しい」と思っていても、「いつ買うべきか?」「いくらまでなら買えるのか?」「住宅ローンの計画はどうすればいいのか?」なかなかわからないものです。
同じ年齢で、収入も同じ人がマイホームを購入する場合でも、適切な予算や住宅ローンは異なります。
たとえば、子どもがいる家庭なら、マイホームよりもまず教育費を優先して確保しておく必要があるからです。必要な教育費の金額は、子どもの人数や、公立か私立か、大学や専門学校など、どんな高等教育を受けさせるかなどの進路によって異なります。現時点では確実なことが決定していなくても、ある程度の方向性を想定したうえで、必要な教育費の金額をあらかじめ計算しておきましょう。
この金額がすでに貯蓄されているか、もしくは子どもの進学までに貯蓄できる目途があるかどうかを確認してから、マイホームに充てる予算や、住宅ローンの月々の返済額を検討します。
また、老後の生活も忘れずに考えておく必要があります。住宅ローンの返済が、リタイア後の家計を圧迫するのは好ましくありません。住宅ローンは、できれば仕事の現役期間中に完済できるように計画しましょう。また、勤め先の定年は何年後か、退職金はいくらくらい受け取れそうか、リタイア後にはどのような生活を送りたいかなどによって、リタイアまでに貯蓄しておきたい老後資金が決まってきます。
老後に生活費が足りずに、せっかく手に入れたマイホームを泣く泣く手放すことになっては残念です。住宅ローンを返済しながらも、老後資金も計画的に貯蓄できるように、マイホームの予算を決定しましょう。
住宅ローンもライフプランに合わせて選べるようになる
住宅ローンは、各々の金融機関からさまざまな種類が提供されています。金利には変動金利、全期間固定金利、固定金利選択型の3種類があります。
変動金利型
変動金利は通常、半年ごとに金利が見直されるタイプです。多くの金融機関では、毎回の返済額が5年ごとに見直され、見直し後の返済額は従前の1.25倍以内というルールになっています。ただし、金利変動の幅には制限はありません。
変動金利は他のタイプに比べて利率が低めに設定されるので、借入当初の返済額をできるだけ低くしたい人に向いています。一方、金利が上昇すると、その分返済額も増えることになるので、まとまった資金が必要なライフイベントを控えている人は注意が必要です。
全期間固定金利型
全期間固定金利は、ローンの契約時点に借入期間中の金利が決定し、変動しないタイプです。長期固定金利住宅ローン「フラット35」や、一部の銀行で取り扱われています。返済額の総額が契約時点で決定するので、返済計画が立てやすいのが特徴です。ただし利率は他のタイプに比べて高めに設定されるので、毎月の返済額が家計を圧迫しないかどうかを検討して選びましょう。
固定金利選択型
固定金利選択型は、借入当初から2年、3年、5年、10年、15年など、一定期間中の金利が固定されるタイプです。固定金利期間中は、金利が変動しません。固定金利期間終了後は、変動金利型か固定金利選択型かを選ぶことができます。その時点の金利でその後の毎回の返済額が再計算されます。一定期間中は住宅ローンの返済額を固定しておきたい、固定期間の終了するタイミングでライフプランを見直したい、という人に向いています。
このように、マイホームを購入するときには、ライフプランを十分に考慮したうえで、予算や住宅ローンを決めることが大切です。
住宅ローン繰上げ返済のしくみ
住宅ローンは長期間にわたる返済計画が大切です。効率的に返済するには、繰上げ返済という方法をとることができます。ただし、必ずしもすべてのケースで繰上げ返済が有効とは限りません。
では、繰上げ返済はどのようにすれば効果的なのでしょうか?
繰上げ返済のしくみと種類
繰上げ返済は、住宅ローンの毎月の返済とは別に、借入金額の一部または全額を前倒しで返済することです。繰上げ返済をすると、返済した金額は元本部分の返済に充てられますので、その分にかかる将来支払うべき利息を減らせます。
繰上げ返済の方法には、「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。
「期間短縮型」は、繰上げ返済に充てる資金を一定期間の元金の返済に充て、その期間分だけ返済期間を短縮する方法です。すると、短縮された返済期間分の利息を支払わずに済みます。繰上げ返済する時期が早いほど、返済期間をより長く短縮できますので、完済が早くなります。
「返済額軽減型」は、繰上げ返済に充てる資金を一定期間の元金の返済に充てて、その時点での残りの期間の返済元金を再計算する方法です。ローンの返済期間は繰上げ返済前と変わりませんが、毎回の返済額が軽減されます。
効果的な繰上げ返済の使い方
「期間短縮型」と「返済額軽減型」のどちらの方法が適しているかは、個々のケースによって異なります。
たとえば、できるだけ早く住宅ローンを完済したい人は、「期間短縮型」が向いています。
一方、住宅ローンの負担が毎月の家計を圧迫している、これから毎月の収入が減るおそれがある、支出が増えるおそれがあるという方は、「返済額軽減型」が向いています。
現在の家計や資産、将来のライフプランをかんがみたうえで、どちらの方法が適しているかを検討しましょう。
単純に、金利の圧縮効果を比べると、同じ返済額、借入利率、借入期間であれば「期間短縮型」の方が大きな効果が得られます。
繰上げ返済を失敗しないための注意点
繰上げ返済には、金融機関所定の手数料がかかる場合があります。手数料を支払ってもより大きな効果を得るためには、できるだけ借入後の早い時期に行うこと、繰上げ返済後の家計に響かないよう余裕資金の範囲内で行うことが大切です。また、複数のローンを借り入れている方は、金利の高い方、借入金額の多い方、残存期間の長い方を優先的に行うと良いでしょう。
実際に繰上げ返済を行った場合に軽減できる利息の金額や、その後の残債額や返済期間は、各金融機関などでシミュレーションをすることができます。あらかじめ繰上げ返済の効果をしっかり確認しておきましょう。
また、期間短縮型で繰上げ返済を実行し、残存期間が10年よりも短くなると、住宅ローン控除を受けられなくなることもあります。繰上げ返済によって得られる効果と、かかるコストや受けられなくなる控除とを比べて、どちらが大きいかを判断したうえで実行しましょう。
繰上げ返済は、住宅ローンを計画的に返済するうえで有効な方法ですが、個々のケースによってその効果は異なります。綿密な返済計画に役立ててみてはいかがでしょうか。
住宅ローン借り換えのしくみ
住宅ローンの効率的な返済には、借り換えという方法をとることもできますが、必ずしもすべてのケースで借り換えが有効とは限りません。では、借り換えはどのようにすれば効果的なのでしょうか?
住宅ローンは長期間にわたるため、返済計画が大切です。効率的に返済するには、借り換えという方法をとることもできますが、必ずしもすべてのケースで借り換えが有効とは限りません。では、借り換えはどのようにすれば効果的なのでしょうか?
借り換えとは、今住んでいる住宅に住み続けながら、住宅ローンを別の金融機関と契約した住宅ローンで一括返済してしまい、新たに異なる条件で住宅ローンを借り入れることです。住宅ローンを借り換えることで今よりも返済の条件が良くなり、効率的に完済できる可能性が高まります。
具体的には、以下の場合には借り換えをすることによって返済の条件が改善することが期待できます。
現在の金利水準の方が住宅ローンの金利より低いとき
現在の金利水準が住宅ローンを借り入れた当初よりも低い場合は、これから新しく借り入れるローンの方が低金利になることがあります。そこでより金利の低い住宅ローンに借り換えることにより、毎月の返済額を抑えることができます。
変動金利、または短期間の固定金利の住宅ローンを借り入れている
変動金利や、固定期間が短い固定金利選択型の住宅ローンを借り入れている人は、将来に金利水準が上がり返済額が高くなるリスクがあります。長期間の固定金利の住宅ローンへ借り換えることで、完済までの毎月の返済額、総返済額ともに確定するため、金利上昇による負担の増加を防ぐことができます。金利が上昇する局面では、借り換えをせずに返済し続けるよりも結果的に総返済額の減少が期待できます。
毎月の返済額の負担が重いとき
住宅ローンの毎月の返済額が大きく家計の負担になっているという人は、借り換えによって毎月の返済額を抑えられる場合があります。必ずしも可能とは限りませんが、ローンの残存期間を現在のものよりも長い住宅ローンに借り換え、返済額を計算し直すことで、1回あたりの返済額を低くできる場合もあります。
借り換えが効果的なのは残り10年以上、1,000万円以上のとき
住宅ローンの借り換えをするには、手数料がかかります。手数料は下記の通り、借り換え前の住宅ローンを完済するためにかかる費用と、借り換え後の新しい住宅ローンを借り入れるためにかかる諸費用があります。
借り換え前の住宅ローンを完済するためにかかる費用
繰上げ返済手数料、抵当権抹消登記費用など
借り換え後の新しい住宅ローンを借り入れるためにかかる諸費用
融資手数料、印紙税、抵当権設定登記費用、団体信用生命保険特約料など
借り換えの効果が発揮されるには、これらの手数料以上に総返済額が減少する見込みであることが必要です。効果があるかどうかは金融機関でシミュレーションをしてもらうことで試算できます。一般的な目安としては、返済期間が残り10年以上、住宅ローン残債が1,000万円以上であれば効果が期待できます。
※借り換えは、借り換え後の金利情勢などによっては、結果的に借り換え前よりも総返済額が増加する場合があります。借り換えの効果は個別のケースによって大きく異なりますので、利用する際には金融機関で必ず詳細を確認しましょう。
教育資金
子どもの教育費は一体いつまでにどのくらい貯めておけば良いのでしょうか?
子どもが生まれたらどの家庭でも気になるのが教育費です。教育費は、人生の3大支出のひとつともいわれますが、一体いつまでにどのくらい貯めておけば良いのでしょうか?
教育費は子ども1人当たり1,000万円とは限らない
子どもに必要な教育費は、よく「1人当たり1,000万円」といわれます。でも、実は全ての人が1,000万円というわけではありません。
必要な教育費の金額は、子どもの進路によって大きく幅があります。公立か私立か、大学に進学するか、専門学校に進学するか、理系か文系かなど、生まれてから社会人になるまでには何度も教育の内容を選択することになります。ここでの進路選択によって、必要な教育費が決まってきます。
オール国公立なら約750万円、オール私立なら2,000万円以上にも
文部科学省の調査によると、学校種別による平成22年度の学習費の総額は以下のようになっています。
幼稚園は公立約23万2千円、私立約53万8千円、小学校は公立約30万4千円、私立約146万5千円、中学校は公立約46万円、私立約127万9千円、高等学校(全日制、以下同じ。)は公立約39万3千円、私立約92万3千円。
つまり、幼稚園3年間でかかる学習費の平均は公立で約70万円に対して、私立なら約160万円、その差はおよそ90万円もあります。この差は子どもが大きくなるとさらに広がり、小学校6年間では公立で約180万円、私立で約880万円、中学校3年間では公立で約140万円、私立で約380万円、高校3年間では公立約120万円、私立約280万円になります。
また、大学に関する調査によると、国立大学では4年間の授業料等の合計は約240万円ですが、私立文系では平均して約390万円、私立理系では約520万円になります。卒業までに6年間かかる医歯薬系ではさらに学費がかかります。私立大学の医科系では6年間で平均約2,360万円、歯科系では約2,500万円にも上ります。大学だけでも、国立大学4年間と私立大学歯科系では約10倍以上もの差があるのです。
したがって、幼稚園から大学までの進路の選び方によって、子どもが一人前になるまでにかかる教育費の総額も大幅に変わります。幼稚園から大学まで、すべて国公立に進学した場合には約750万円ですが、すべて私立で、理系大学に進学した場合には2,000万円以上になります。子どもが生まれたらある程度の方向性を決めて、できるだけ早めに貯蓄を始めることが大切です。以下にコースごとの教育費の総額をまとめましたので、参考にしてみてください。
◇オール国公立コース:約750万円
(幼稚園・公立→小学校・公立→中学校・公立→高校・公立→大学・国立)
◇大学のみ私立文系コース:約900万円
(幼稚園・公立→小学校・公立→中学校・公立→高校・公立→大学・私立文系)
◇高校から私立、大学は私立文系コース:約1,060万円
(幼稚園・公立立→小学校・公立→中学校・公立→高校・私立→大学・私立文系)
◇中学から私立、大学は私立理系コース:約1,430万円
(幼稚園・公立→小学校・公立→中学校・私立→高校・私立→大学・私立理系)
◇小学校から私立、大学は私立理系コース:約2,130万円
(幼稚園・公立→小学校・私立→中学校・私立→高校・私立→大学・私立理系)
教育資金の準備
積立以外にも、こども保険、学資保険、一般財形の利用、公的教育ローン、民間金融機関教育ローン、奨学金制度などが活用できます。
このように、子どもの教育費はまとまった資金が必要で、進路によって大きな差があります。ご自身の大切なお子さんが希望する学校に進学できるよう、計画的に教育資金を貯蓄しましょう。